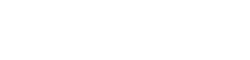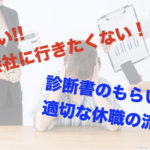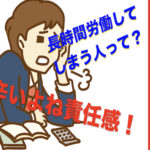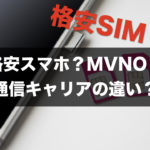魔の2歳児と言われるこの時期は本当に大変です。ご飯を食べるのも着替えもお風呂も、とにかくなんでもイヤイヤで悩むママやパパも多いかと思います。
子供自身もやりたいことと自分ではできないこととの狭間で悩んでいる時期。
親の言うことを聞いてくれれば楽だけどイヤイヤ期になると自我が芽生えて自分の思い通りに子供は動いてくれません。
そんな悩むママやパパに10の向き合い方を意識して子供と接すると上手に子供と向き合えるようになります。
今回はイヤイヤ期を乗り越える対処方法をご紹介していきます。
イヤイヤ期の特徴や時期
早い子で2歳から始まるイヤイヤ期。このイヤイヤ期とは子供が成長過程で2度訪れる反抗期のうちの1回目「第一次反抗期」のことを指します。
反抗期(イヤイヤ期)は子供の成長過程
「反抗期」と言うと、ネガティブに思いがちですが、小さい子供にとっての第一次反抗期は、心が健全に成長発達するために欠かせない成長過程です。
イヤイヤ期の子供の過ごし方でその後の子供の人格形成や第二次反抗期の現れ方に影響を及ぼすことが分かっています。
イヤイヤ期の特徴
イヤイヤ期の特徴は、次の3つです。
- 子供の自己主張が強くなり大人の言うことに対して「イヤ」と反抗する。
- 難しそうなことも自分の力でやりたがる。また、自分の力で挑戦してもできない時は癇癪を起こす。
- 自分の思い通りにならないことに対して攻撃的になったり、泣きじゃくったりする。
幼児期に入ると、パパやママとは違う意思や感情があることを自分で自覚し、一人の人間だという認識を強め、自分の意思で行動や意思を表現するようになります。
いわゆる「自我の芽生えと発達」です。
親にとってのイヤイヤ期とは
親にとってのイヤイヤ期は、「わがままや親への全身を使っての抵抗、うるさく泣き叫び子供に振り回される」いちばん大変な時期になります。
特にママやパパをイライラさせる具体例として反抗や抵抗が強く現れるタイミングが悪いことがあげられます。
- 公園で遊んでいて途中で切り上げて家に帰る場合や別の行き先にいく必要があるにもかかわらず子供は「まだ公園で遊ぶ!」と反抗。
- 行き先が決まってるのに自分の行きたいところを指差し「あっちに行きたい!」と逆方向に行きたがる。
- 親の時間がないにもかかわらず保育園や幼稚園の送迎時に寄り道をしたがったり、「行きたくない!」泣きわめき抵抗する。
- 子供の生活習慣の「お風呂」「歯磨き」「睡眠」を嫌がる。
- 食べ物に対して好き嫌いを言い嫌いな食べ物を食べない。
- 「抱っこ」と言い張り自分の力で歩こうとしない。
こういった事で計画通りに進まないためパパやママはイライラを募らせたりします。
時間も取られパパやママの自分の時間は完全になくなるため、精神的にも体力的にもストレスを感じる時期になりますね。
イヤイヤ期を乗り越える10の方法

イヤイヤ期を乗り越える対処方法として重要なのは親の心の面や子供に使ってあげる時間の取り方が重要になります。
ここではイヤイヤ期を乗り越える10の対処方法をご紹介します。
子供を頭ごなしに叱ってはいけない
イヤイヤ期の特徴はいずれも子供の遊びたい、やりたい、欲しいという自己主張です。
赤ちゃんの時は自分の欲求を泣いて表現し大人に伝えることしかできなかったのに、イヤイヤ期を迎える頃には少しずつ言葉も覚え、体力も付いているためバリエーション豊かに自己主張ができるようになっています。
子供の豊かな自己主張は、周囲に対して自分に興味を向けさせて伝えることができる証であり人間の最大の力と言えます。コミュニケーション能力は集団生活や子供の運動、遊び、勉強などあらゆる場面で必要になる能力です。
そのため、頭ごなしに叱って押さえつけるのではなく、「わがまま、反抗=悪いこと」ではないという考え方を持って、子供の自己主張をうまく引き出しながら、思い通りにはならないこともあることを教えてあげることが大切です。
子供にとって一番の理解者にあたるパパやママが頭ごなしに子供を叱りつけてはいけません。
「わがままや反抗=子供のコミュニケーション」という考え方を持って、子供の自己主張をうまく引き出しながら、理解し思い通りにはならない時は優しく教えてあげることが大切です。
パパやママが感情に任せて怒鳴ったり暴力してはいけません(キレてはダメ)

自分の思い通りにならないからといってパパやママが子供に対して感情に任せて怒鳴りつけてはいけません。
自分より体が何倍も大きい大人に、大きな声で怒鳴られたり暴力を振るわれたりする事や、親という子どもにとって絶対的な存在に怒鳴られることで子どもの心は恐怖で萎縮してしまいます。
子どもに怒鳴ることや暴力は子どもの精神を大きく傷つけ子供の成長に強く悪い影響を与えてしまうため絶対にダメです。
どんなにイライラしたりストレスを抱え込んでしまっても一呼吸置いたり、深呼吸したり、子供の笑顔を思い出したりして自分の心を落ち着けてください。
子供に対してパパやママが言ってはいけない言葉や発言

パパやママは子供のしつけをする上で意識して言葉選びをしないといけません。その理由は子供に対して親が不適切な発言を繰り返すことで子供も自分の友達たちや周囲の人に対して親と全く同じ行動をとったりするようになってしまいます。
また、子供を深く傷つけてしまう場合だってあります。
パパもママも知らない!勝手にすれば!
例えば外出時によくある光景で、嫌がる子供に対して服やコートを何とかなだめて着せて、ようやく子どもに靴を履かせようとしました。すると今度は「嫌!履かない!」
そして、靴を履かせるのに格闘。
出かける時刻がどんどんと遅くなりパパやママのイライラがピークに達します。
そんな時、「勝手にすれば!もう知らない!」と叱ってしまうのはよくありません。
まだ幼い子どもにとって、親に突き離される言葉は一番傷つくのです。子供は一気に悲しみの淵に立たされ泣きじゃくります。
言うこと聞けないならオヤツ無し。遊び無し。
常に交換条件をするような言い方で叱りつけることで子供は罰則条件が出される時しか言うことを効かなくなります。
いい加減にしなさい!怒るよ!
既に叱りつけているにもかかわらず更に厳しい表情で強く大きな声で追い打ちをかけるように「怒るよ!」を付け加えれば、恐怖をさらに植えつけることになります。
恐怖心による叱りつけは子供を一時的に親に服従させ言いなりにさせることはできますが、子供の精神面の成長では萎縮してしまい悪影響を与えかねません。
ダブルバインドをしないように意識すること

ダブルバインドとは、二つの矛盾した命令をすることで、相手の精神にストレスがかかるコミュニケーション状態を意味します。
簡単な例をあげるとこうです。
「もう帰るよ」と言って「まだ遊ぶ!」と主張する子ども。「じゃあ勝手にしなさい、バイバイ」と、帰るふりをするパパやママ。
「もう帰るよ」と言う最初の命令と「じゃあ勝手にしなさい」と言う2つの矛盾した指示になります。
子供は「帰るよ」と「勝手にする」を理解することはとても困難です。
こう言った「二重拘束」を与える伝え方をする事で子供は親を真似るようになっていきます。
例えば子供が自分の思い通りにならなからと言って友達に対し「おもちゃを貸してくれないんだったら、もう一緒に遊んであげない!」など将来、親と同じことを繰り返すようになってしまいます。
ダブルバインドは自然と使ってしまいがち
子供をコントロールしたい気持ちで自然と使ってしまいがちです。そのため、親は意識しなければいけません。
会社で言えば部下や新入社員の教育係になった気持ちになる必要があります。
例えば、新入社員に対して「○○しろ」と指示し「それならどうしたらいいのか?」を聞かれたのに「そんなことは自分で考えろ!」と怒る事です。
こう言ったやり取りは大人になっても多く使われたりするため、子供にも自然と使ってしまいがちです。
矛盾した二重拘束を与える発言は意識してやめましょう。
子供の気持ちに寄り添った言い方を心がける
イヤイヤ期は感情のコントロールを学ぶので、毎回、パパやママが子供の無理な要求を聞き入れていると、「泣けば言うことを聞いてもらえる」と学習してしまいます。
かと言って恐怖心やダブルバインドで子供を従わせては成長の妨げになります。
大切なのは、ママやパパが「○○するのはイヤなんだね」と感情は受け止めてあげる事です。そして、パパやママがしたいことに対して行動はゆずらないことを心がけましょう。
「やりたくない!」という主張は受け止めながらも、子供に対して何でパパやママがそうしたいか理由を丁寧に伝えましょう。
それでも言うことを聞いてくれない時は「あと○回だよ」と限定話法を使ったりするといいです。
パパやママが自分に理解を示した上で許しが限定で出たことでキッチリ切り上げて親の言うことを聞いてくれたりします。
30分前行動で心に余裕を作る

イヤイヤ期に突入した子供はとても多感です。興味を持ったものに対してまっしぐら。
そんな子供と行動する時は30分前行動を心がけましょう。
例えば、朝の保育園や幼稚園の登園時間や仕事の時間に追われ急いで行くケースがあります。
そんな時に限って子供が公園で遊びたがったり、保育園や幼稚園に行くことを拒絶することがあります。無理やり連れて行こうとすると強い抵抗を見せ余計大変なことに。子供が強く抵抗しだすと計画通りに行動出来なくなってしまいパパやママも大変に。
そうならないためには最初から早い行動をするといいでしょう。子供と行動をする時は想定の倍以上の時間がかかると予想し行動していると、大人がイライラしてしまう回数も減り、心のゆとりができるため笑顔で対応してあげることができます。
子供が公園に行きたがるのであれば、事前に公園に行ける時間を用意して行動すると良いです。子供も30分も公園で遊べば満足しパパやママの言うことを聞いてくれるでしょう。
他にも道草してしまう子供であれば、道草してしまう分の時間を確保して動くことをする事でパパやママも時間に追われることを防ぐことが出来ます。
子供が何かをしている途中、無理やり切り上げさせようとすると強い抵抗を示します。
なのである程度満足ができる時間を用意してあげれば子供もイヤイヤせずに言うことを聞いてくれます。
自分のペースで動けないことや時間を早く行動することはママやパパにとって大変なことかもしれませんが、子供が抵抗してイヤイヤされるよりは楽だと思います。
イヤイヤ期こそパパが育児に当てる時間をいっぱい取ること

イヤイヤ期前はママ一人で育児をしていても子供は小さくママのペースで育児ができたと思います。
しかし、イヤイヤ期の育児はとても大変な時期です。子供は元気いっぱいに動き回り、言葉も爆発的に話すようになります。そこに自己主張が加わるためママの思い通りに育児は進まなくなります。
そんな大変な時期だからこそパパは育児にたっぷり時間を取ってあげるといいですね。特にママにほとんどの育児を任せている場合はパパの変化が必要です。
普段は子供と休日だけ遊ぶだけだったり、休日だけ子供の世話をするのではなく毎日ママのサポートができるようにしてあげるといいですね。
特に子供の食事、お風呂、寝かしつけ、保育園の送迎、歯磨き、掃除はパパも積極的に実施しましょう。整理整頓された綺麗な環境だったり、子供の基本的な生活習慣のしつけがとても重要なためパパも子供との遊び以外のスキルを磨きママと一緒になって子供の世話をしてあげるのがいいです。
パパの育児参加時間が増えることでママの精神面や肉体面を支えることができるようになり、より良い家庭環境を築くことに繋がります。
パパが好き?ママが好き?かは関係ない
「子供がママになついている」「私よりパパに懐いている」とお悩みの親も多いかと思いますが気にする必要はありません。
メインの保育者を決めるのは子供になるので、子供が今現在一緒にいて落ち着く方を選んでいるだけになります。
決してママが嫌いだったり、パパが嫌いだったりするわけではないです。
むしろ、どんな時でもパパやママのところへ飛び込んで行ける環境を用意してあげることが重要です。
今はママに懐いていても、いつでもパパのところに飛び込んで来てもいいよと思う気持ち子供としっかり接することで飛び込んで来ます。
「自分でやりたい」を尊重しチャレンジ精神を植える
イヤイヤ期の子供は親が決めた物や遊びをやりたがりません。また、靴の履くことや服の着脱も自分でやりたがったりと、なんでも最初は自分でやりたがります。
そんな時にパパやママに時間が無いからといった理由や今の子供のレベルではできないといった理由で親が止めてしまうのはよくありません。
イヤイヤ期による自我の芽生えは「挑戦」や「チャレンジ精神」を子供に植えつけていく重要な時期です。
子供のチャレンジに対して親が強制的に介助や仲介、阻止をしてしまうと子供の成長の妨げになりかねません。
最初は「子供の気のすむまでやらせてみる」を心がけてください。
子供に選択肢を提示して「選んでもらう」
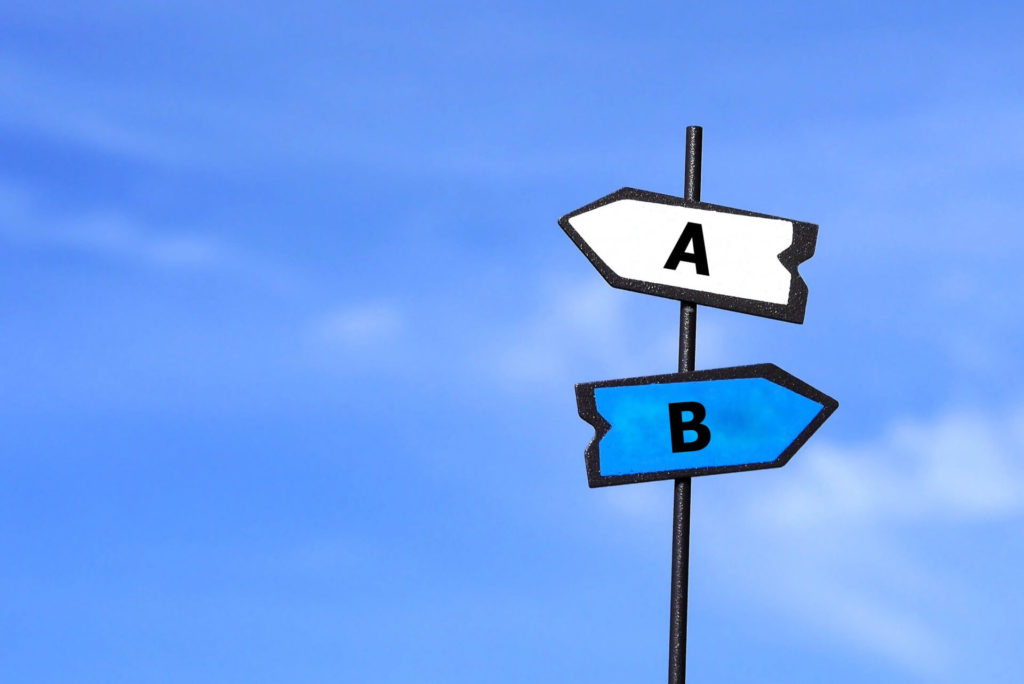
イヤイヤ期では難易度を気にせず子供は興味を抱いた物に対してチャレンジしようとします。大人から見て難しい事だったりする場合、親が最初からやってしまうことってありますよね。すると子供は「自分でやる」と泣きじゃくったり不機嫌になってしまったりといったことおきます。
そのため、何かをやりたがったり、やらせたい時は「自分でやる?それともママやパパがやる?」ことを選択肢に入れて質問を子供にするといいですね。
子供に選択肢を与えることで子供は「自分で決定した」ことを理解するためパパやママにやってもらっても満足します。
まとめ
イヤイヤ期に突入した子育て期間は親にとって一番大変な時期と言われています。
逆に子供にとっては「自我の芽生え」という成長過程でとても重要な時期になります。子供の成長を促していくために親が子供と真正面から多くの時間を使って向き合ってあげることを心がけることでしっかりと乗り切ることが出来ます。
子供の変化に合わせてママもパパも適応していくことでイヤイヤ期でもスムーズに子育てが出来ることでしょう。そして、何よりも子育てを楽しむことが重要です。
そして、魔のイヤイヤ期を「子供と楽しむイヤイヤ期」に変えていけるといいですね。