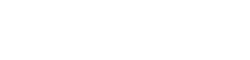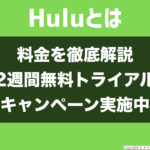男性が育休を取得する上でどんな育休制度があるのか、そして一番不安になる家計への影響や育児休業給付金について知らない男性は多いと思います。
そこで今回は育休手当関連で、支給されるお金について、実際にいくら支給されるのかも含めまとめたいと思います。
育休を取得する前にちゃんとした認識が持てるようにしておきましょう。
男性の育休は2種類も用意されている
日本では男性の育児休業を促進するために2種類の制度が利用できるようになってます。
「パパ休暇」について
一つ目は子供が産まれてから8週間以内に育休を取得した男性が、再度育休を取得できる制度が「パパ休暇」です。
「パパ休暇」のメリット
出産後、8週間以内はママの出産後の体調が戻らない辛い時期をサポートすることが出来ます。そして、いったん職場に復帰した後でも再度、男性は育児休業を取得することができます。
パパ休暇で男性が再度、育休が取得出来る背景は「パパの育児への積極参加」と「ママの職場復帰のサポート」が出来るようにするために設けられた制度となっています。
「パパ・ママ育休プラス」について
「パパ・ママ育休プラス」は両親ともに育休を取得する場合に子供が1歳2ヶ月になる間で取得できる制度です。
「パパ・ママ育休プラス」の取得条件
- 子供が1歳に達するまでに、配偶者が育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
「パパ・ママ育休プラス」のメリット
- 通常1歳までの育休を1歳2ヶ月まで延長出来ることで交代で夫婦交代で育休を取得が可能。
- 育児休業給付金の給付率67%支給期間(6ヶ月間)を互いに交代交代で上手に利用できることが可能。
- あとから育休を取得したパパもしっかり長い期間、育休を取得できるようなっている。(通常、育休は妻が先に取得して後から男性が取得する傾向があるため)
男性の育休中の給与と育児休業給付金

ほとんどの企業で育休中は、基本的には無給です。
そのため夫の給与が一時的に無くなるのは家計にとって大きな打撃になると考える人が多いようです。
そのかわり男性が育休を取得する場合も女性と同様に「育児休業給付金」を受けとることができます。
育児休業給付金はどこから支給されるの
育児休業中に支払ってもらえないお給料の代わりに、国が支給してくれる育休手当のことを「育児休業給付金」と「育児休業手当金」といいます。
- 民間企業に勤めている会社員…雇用保険から育児休業給付金が支給される。
- 公務員…共済から育児休業手当金が支給される
育児休業給付金は、社会保険のなかの「雇用保険」が財源になっていて、雇用保険に加入している被保険者が受け取れる給付金です。
つまり、会社員の場合は社会保険に加入しているので対象になります。
育児休業給付金の申請
育児休業給付金の申請は基本的には会社を通じて申請します。
ご自身で行う場合は、会社が管轄しているハローワークに直接申請することが必要です。
申請期間
育児休業給付金の手続きを希望する場合、まずは受給資格の確認を行う必要があります。
受給資格の確認は原則として勤務先が行います。受給資格の確認が取れると初回の申請に必要な「育児休業給付受給資格確認通知書」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」が交付されます。
勤務先を通して手続きを行う場合は受給資格の確認及び初回の支給申請は同時に提出できるので、勤務先から書類を受け取り、必要事項を記入して提出すると楽です。
書類が正しく受理されて育児休業給付金の支給が決定すると、指定した口座に約1週間ほどで振り込みがされます。
2回目以降の申請は、勤務先を通して2カ月に1度申請を行うことになります。
本人が希望すれば1ヶ月に1度の支給申請も可能です。その場合は申請期間も異なってくるので必ず確認しましょう。
育児休業給付金の支給額はいくら
実は男性の場合、育児休業給付金が女性と比較して支給額が多い傾向にあります。
その理由として、男性の場合が女性とよりも給与が高いケースがある上に下記計算式で育児休業給付金が決まる仕組みになっているからです。
育児休業給付金の計算式
休業開始時賃金日額×支給日数×給付率67%(180日間まで)
休業開始時賃金日額×支給日数×給付率50%(181日以降)
休業開始時賃金日額とは
休業前の6ヶ月間の給与(ボーナス除く)合計を180日で除した額。
※基本給に諸手当を含めたもの=住宅手当や通勤費などを計算に入れるものです。
例えば直近6ヶ月間の給与明細で控除前の額面が下記の会社員の場合
- 基本給 30万
- 残業代 6万
- 交通費 1万
- その他手当 3万
この場合は合計月額は40万円/月となり、過去6ヶ月間の合計額は240万になります。
あとは180日で除したら「休業開始時賃金日額」が算出されます。
この会社員の「休業開始時賃金日額」は約13,333円となりますね。
支給日数とは
30日で計算します。
給付率とは
給付率は育児休業期間に応じて変動するものになります。
2019年3月現在だと育休180日以内は67%の給付率。181日以降は50%の給付率になります。
例にあげた会社員の場合なら180日間は1ヶ月の支給額が268,000円となります。
181日以降は200,000円となります。
支給額の上限と下限について
支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が449,700円を超える場合は、「賃金月額」は、449,700円となります。
つまり支給上限額は180日間は301,299円、181日以降は224,850円となります。
「賃金月額」が74,400円を下回る場合は74,400円となります。(この額は毎年8月1日に変動してます。)
育児休業給付金は非課税
育児休業給付金は非課税です。所得税はかからない上、翌年度の住民税算定額にも含まれません。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されるため、先述の育児休業給付金からの控除はありません。
その結果、育児休業取得前の手取り賃金と比べると休業前の最大約8割が育児休業給付金として受け取れるのです。
男性の育休が原因で家計の破綻は考えにくい
育児休業給付金について理解が深まったと思います。
ここまで読んでみると男性が育休を取得したからといって家計の破綻は意外とない事に気づいた人は多いのではないでしょうか?
30代の育休は経済リスクがない

最近は共働き家庭も多く夫婦共に育休を取る家庭も多い点、晩婚化によって第一子の出生年齢は男性も女性も30歳を越えています。
30歳をすぎた年齢と言えば社会人として経験を積みキャリアが乗って年収も若い頃と比べて上がってる人が多いです。
また、20代と違い貯蓄を行ってる人も多く、普段の金遣いが荒い家庭ではない限りは一定期間の収入減でも家計破綻は考えにくいです。
30代だからこそ安心して育児休業が取れる
30代は社会人経験を積みスキルもある上に体力もあります。
そんな時に職場から離れることがマイナスになってしまうのでは?と考えてしまう人も多いでしょう。
でも、30代だからこそ多少のブランクを作ってもスグに取り戻せるのも事実です。
20代で下積み時代を経験した30代は仕事の応用力も高く処理スピードも人脈もスキルも圧倒的に強くなっています。
そんな20代の下積みの経験が一定期間休業したからって無くなるわけではありません。
自信を持って堂々と休んで平気ですよ。
世間体を気にしすぎる30代だからこそ育休をネガティブに捉えてしまうのは理解はできます。
しかし、経済的なリスクも大してなく、ママや生まれてきた子供と貴重な時間が過ごせる期間は育休しかありません。
逆に、こんな30代にとって有利な育児休業制度を利用しない方がもったいないです。
まとめ
男性の育児休業の仕組みはある程度、理解できたのではないでしょうか?
ここまで、読んだパパ・ママは少なからず育休を視野に入れているだろうと思います。
私も実際に育児休業を取得して経済的な不安というものは一切なかったです。
ただ、私の場合は正確な制度や給付金について知ったのは育児休業を取得してからでした。
育休準備段階から制度への理解や育児給付金への理解を深めておく方が夫婦にとって良い準備や不安のない育休開始ができるのです。
育休を検討しているパパは前向きに制度を理解し活用して育児と家事をママと一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。